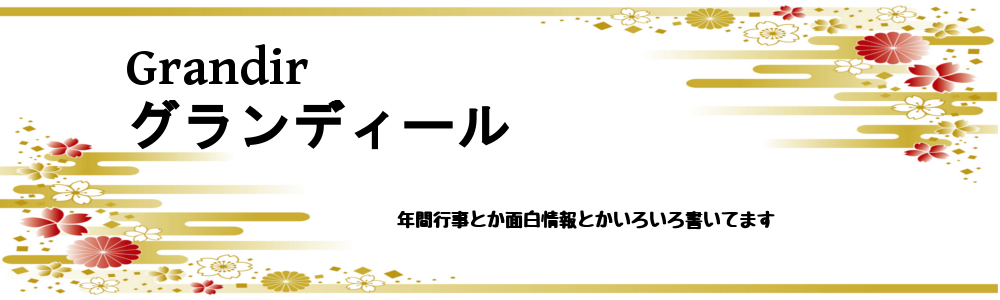1月7日は七草がゆを食べる日ですね。
今では、お正月明けの習慣として定着している行事の一つになっていますよね。
なぜ、1月7日に七草がゆを食べるのか?その意味や由来、そして、実際の栄養素や効果などをまとめてみました。
七草がゆを食べる意味といつ食べるの?
1月7日に昔から食べることになっている七草がゆ。
食べたことあるよという方も、聞いたことはあるけどね、という方も様々だと思います。
私が子供の時に聞いた話では、お正月にごちそうを食べすぎたりお酒を飲みすぎたりして疲れた胃腸を休めて、普段の生活に戻っても体調を崩さないようにするためと松の内も終わるので、お正月にいったん区切りをつけるため、ということでした。
家でもそう聞いていて、学校の授業でも、そういう話を聞いた覚えがあります。
では、一日3食のうち、どこで食べるのが本当なのか?といいますと、やはり、朝食べる、というのが良いようです。
起きたばかりの体に優しいおかゆで・・・ということなのでしょうね。
しかし、この七草がゆの意味は、どうやら後付けされた意味のようで、本当の由来や意味はもっと違うところにあるのです。
七草がゆを食べるようになった本当の由来はどこから?
七草がゆを1月7日に食べるようになった本当の由来は、中国から伝わったものです。
七草がゆを食べるという風習は奈良時代までさかのぼります。
日本には古来から、年の初めに芽吹いた若菜を摘んで食べる「若草摘み」という風習や、1月15日に米、あわ、ひえ、きび、ごま、小豆、みの米という7種類の穀物でおかゆを作る「七種がゆ」の風習がありました。
そこへ、中国から1月1日から7日にかけて連日家畜の運を占うという文化が入ってきました。
1月1日から鶏、犬、いのしし、羊、牛、馬と順番に占っていき、7日目に人の運勢を占い、「七種菜羹(ななしゅさいかん)」という汁物を食べ、無病息災を願う、という風習です。
この中国の文化と日本の文化が結び付いて日本の文化として根付いたということです。
最初は今言われている「七草がゆ」ではなく「七種がゆ」と書いて「ななくさがゆ」と読んでいました。
春の七草もセリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロというのも最初からではなく、1360年代に『河海抄(かかいしょう)』という書物に、四辻善成が春の七草として紹介したことから始まったのです。
当時は、貴族社会の儀式としてのみ行われていたもので、庶民にはなじみがなかった習慣でした。
江戸時代に、中国から伝わった1月7日に人を占う文化から、この日を「人日の節句」と定め、庶民に広がったということから、今の風習として残っているのです。
七草がゆの栄養素と効果は?
「人日の節句」ということで無病息災を願い食べる行事食の七草がゆですが、実際のところその栄養と体への効果、というのはどのようになっているのでしょうか?
セリ・・・鉄分が多く含まれているので増血作用が期待できる
ナズナ・・熱を下げる、尿の出をよくするなどの作用
ゴギョウ・・かぜの予防や解熱作用がある
ハコベラ・・タンパク質が比較的多く含まれ、目に良いとされるビタミンAが豊富で、古くから民間で薬草と使用されることもあり、腹痛の薬にもなったそうです。
ホトケノザ・食物繊維を豊富に含んでいます
スズナ・・・カブのことで、食物繊維、ビタミンが豊富です
スズシロ・・大根のこと、食物繊維、ビタミンが豊富でジアスターゼという消化酵素も含んでいます。
ざっと栄養素を書いてみましたが、簡単に見ただけでも、鉄分、たんぱく質、食物繊維やビタミンを含んでいるものばかりなので、お正月で食べすぎた胃腸をいたわり、寒い冬を乗り切るのに最適な食べ物、というのも正しい解釈です。
また、利尿作用のあるものも入っているので、汗をかきにくい冬の時期、むくみ解消にもおおいに役立ってくれそうです。
これは、冬の食べ物として、積極的に食べたほうがよいようですね。