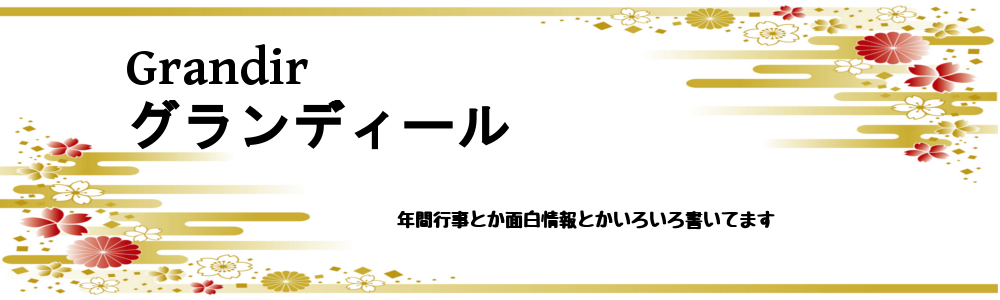立冬って何の日でいつ?何か食べたほうが良い食べ物とかあるの?
カレンダーを見ていて「立冬」と書いてあるのを不思議に思ったことはありませんか?
立冬って何の日で、いつなの?立冬に食べたほうが良い食べ物は冬瓜だそうです。なぜ冬瓜?どんな料理があるの?
立冬ってそもそも何の日なの?
カレンダーを見ていると「立冬」と書いてあるけどこの日はいったい何の日なのでしょうか?
立冬とは、中国の二十四節気(にじゅうしせっき)という暦の中のもので。立春、立夏、立秋、立冬と四立(しりゅう)と言われるもののひとつです。
それぞれの季節の始まりの日となります。
つまり、立冬とは秋の終わりで「冬の始まり」の日となります。
この日から立春の前日までが暦の上では「冬」となります。
この日を境に、気温が急激に下がることが多く、冬の訪れを感じ始めることでしょう。
立冬とはいつ?
立冬とは二十四節気という暦の中のひとつで、立春を一年のはじめとすると第19番目にあたります。

太陽の移動に合わせて季節の変化を表す「二十四節気」。
もともとは、中国で生まれた暦で、太陽の動きに合わせて一年を24に分けて季節を区切っています。
その中で立冬は太陽の通り道が225度のときで、冬至から数えて約319.59日後のこと、おおよそ11月6~8日くらいが当てはまることが多いが、毎年その日は変動するのです。
節分が2月3日だったり4日だったりするのと同じ考え方です。
2017年は11月7日が立冬に当たります。
洋服の衣替えもこのころを目安にするといいかもしれません。
立冬の食べ物おすすめは冬瓜。 どんな料理法がある?
立冬は冬の始まりの日です。
この日を境に急激に気温が下がり始め、冬へと季節は移っていきます。
この日に何か食べたほうがいいものは特にはないようですが、寒い冬を乗り越えるために体を温める食べ物を積極的にとるとよいかもしれませんね。
ただ、昔は、冬瓜を食べることが多かったようです。
冬瓜とは、夏の野菜なのですが、日持ちが良く、夏に収穫され、冬まで保存することができるということで「冬まで持つ瓜」ということで冬瓜という名前が付いたといわれています。
冬瓜は95%が水分であり、カリウムを多く含みます。
カリウムには塩分を排泄する役割があるので、むくみ対策に良いかもしれませんね。
肌の健康維持や風邪などに対する抵抗力を高めるビタミンCを含んでいるので、風邪対策として冬の始めの立冬に食べるとよいのかもしれませんね。
では、冬瓜はどのようにして食べるのが美味しいのでしょうか?
一般的にはひき肉と煮込んでそぼろあんかけで食べるのが有名ですが、他になにか美味しい食べ方はないのか探してみました。

作り方はこちら↓
こんな感じに料理すると冬瓜もおしゃれですよね。
今年の立冬は冬瓜をおしゃれに料理して食卓に並べてみませんか?