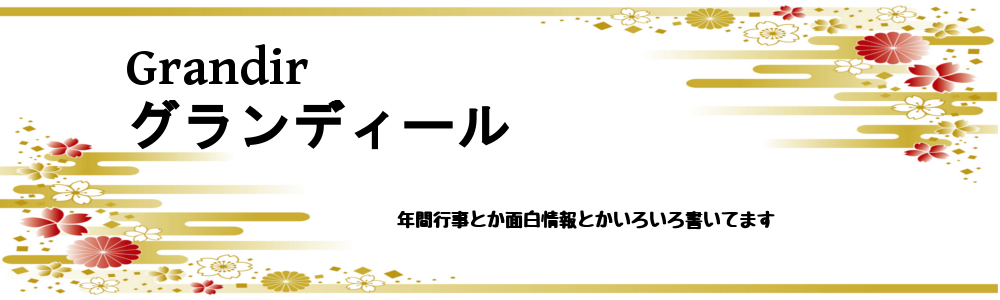小寒とは二十四節気の中のひとつです。寒の入りとも言われていてこの日から冬の寒さが本格的に厳しくなる時期とされています。
小寒の時期は年明け早々なので、寒さが厳しくなる時期とはいえ、まだまだ松の内。お正月のイベントが続く時期です。
楽しいイベントや食べ物で寒さを吹き飛ばしましょう。小寒の意味とイベントなどについてまとめました。
小寒はいつ?どういう意味?
小寒とは二十四節気の23番目に当たります。
「小寒」と書いて「しょうかん」と読みます。
時期的には冬至から15日目にあたり、だいたい1月5,6日あたりです。
この日のことを指すこともありますが、正確には、この日から15日後の大寒までの間の時期をさします。
この小寒の始まりの日のことを寒の入りという呼び方をし、冬の寒さが最も厳しい時期に入るという意味になります。
この寒さは大寒が最も厳しく、大寒から15日後の節分まで続き、立春で終わりになります。
立春を「寒の明け」という呼び方をします。
小寒のころのイベントや食べ物って何があるの?
小寒はその年によって1月5日か6日になりますが、まだまだお正月も松の内のころ。
仕事初めで、仕事が始まっている人が多い時期ではありますが、まだまだお正月気分が抜けきらない時期ですよね。
そのころに重なるイベントとしては水産業の卸市場の初ぜり。
マグロの初ぜりなどが行われ、初マグロが驚くような値段で競り落とされるのがこのころになります。
また、1月7日は七草がゆの日。
お正月のごちそう三昧で疲れた胃腸を優しく癒すお粥を食べたり、1月11日鏡開きで鏡餅を割ってぜんざいやお汁粉を食べたり1月15日小正月で小豆粥を食べたりと、暖かい食べ物を食べる機会が多くなります。
寒さが厳しくなる小寒の時期、風邪をひかないように体を温める食べ物を食べて、寒さを乗り切っていきましょう。