
立冬は冬の始まりの日。
立冬を境に日ごとに気温が下がり、寒い冬へと向かっていきます。
寒い冬を迎えるにあたり、冬の始まりの立冬の日に中国では餃子を食べる習わしがあるといいます。
日本は寒くなる季節の始まりは「鍋の日」。では体が温まる餃子鍋はいかがですか?なぜ中国では立冬に餃子を食べるのか?日本はなぜ鍋の日?
家庭でも簡単に作れる体が温まる餃子鍋のレシピとコツをご紹介します。
立冬に中国では餃子を食べるのはなぜ?
中国では立冬に餃子を食べるという習わしがあるそうです。
南の地域では鶏肉やアヒルや魚を食べるそうなのですが、北の地域、北京や天津辺りは餃子を食べるそうです。
餃子の始まりは中国の「祛寒嬌耳湯(耳の凍傷を防ぐ効果のあるスープ)」に由来するとのことです。
昔、中国に「医聖」と称えられた張仲景という人がいました。
張仲景は長沙の、今の日本でいう県知事のような官職を退官して帰省した際に熱病が流行っているのに出くわしたそうです。
そこで、飢えと寒さのために両耳が凍傷になった多くの民衆を見て、この人たちを何とかして助けたいという思いから体を温めるスープを作ることを考えました。
 (写真はイメージです)
(写真はイメージです)
そのスープの具材となったものは、羊肉と唐辛と体を温める薬膳を入れて煮込み、それを小麦粉で包んでさらに煮込んだものでした。
寒い冬にこのスープを飲んで人々は熱病を抑え、耳の凍傷も治ったといわれています。
この小麦粉で包んだ具材の形が耳の形に似ているところから「餃耳」と呼ばれ後の「餃子」になったということです。
中国では「餃子」と言えば水餃子が多く、餃子はこの伝説がもとになったといわれています。
北京では冬はマイナス15度にもなるといいます。露わになっている耳が凍傷になってもおかしくないくらいの寒さです。

そこで、冬の始まりの立冬に冬の寒さで凍傷になって耳が落ちないように、形が耳に似た餃子を食べるという意味もあるということです。
さらに、中身の肉は、羊の肉が体をあっためる作用があるために、立冬で使う肉は羊の肉を使うことが多いようです。
立冬は日本では鍋の日
日本では、立冬に何を食べるという習わしはこれと言ってないようです。
保存食としての冬瓜を食べる、という風習も聞いたりしますが、特に決まり、ということではないようです。
しかし、立冬から気温が下がりだす季節の変わり目、ということで、体を温める食べ物を食べたほうが良い、という考え方はあります。
そこで、体を温める食べ物の代表として「鍋」を推進するために、鰹節やだしの素などで有名な食品メーカー「ヤマキ」が11月7日を「鍋の日」に決めたそうです。
立冬はその年によって若干の日にちのずれはありますが、おおむね11月7日になることが多いから、というのも理由の一つのようです。
気温も下がりだし、日中の明るい時間帯も少しづつ短くなってくるこの立冬の時期。
家族で暖かい鍋を囲むのも気持ちも体も暖かくなりそうですよね。
簡単!餃子鍋で体を温めよう!
立冬に中国では餃子を食べ、日本は鍋の日なので、立冬に餃子鍋はいかがでしょう?
冬に向かって気温が下がると体温も下がり、体調も崩しやすくなります。
インフルエンザもそろそろ流行り出す時期。
暖かい鍋に餃子を入れて、心も体も温まりましょう。
そこで、11月7日を鍋の日と決めたヤマキのホームページに、立冬にぴったりな
「ネギたっぷり餃子鍋」のレシピがありました。

ネギをたっぷり入れた餃子鍋。
体の芯から温まりそうですよね。
ネギたっぷりの餃子鍋のレシピはこちら⇒★
餃子を手作りされるなら、中身の肉を羊にするというのもいいかもしれません。
でも、そこまで手間暇かけられないという方には、入れるだけ簡単な水餃子があります。
味の素冷凍食品)皮もちもち水餃子 約12.5g×50個入(業務用食材 餃子 ギョウザ ぎょうざ 中華料理 ビール)
価格:1023円(税込、送料別) (2017/9/24時点)
この出来合いの水餃子なら、鍋にそのまま入れても大丈夫ですが、手作りで餃子を作られる場合は、一度、熱湯で餃子を茹でてから鍋に入れるようにしてくださいね。
茹でないで鍋に入れてしまうと、餃子の形が崩れてしまって、ドロドロになってしまう・・・なんてことになってしまいます。
餃子鍋をされる方は、ご注意くださいね。
では、暖かいものを食べて、寒い冬を乗り切りましょう!!!
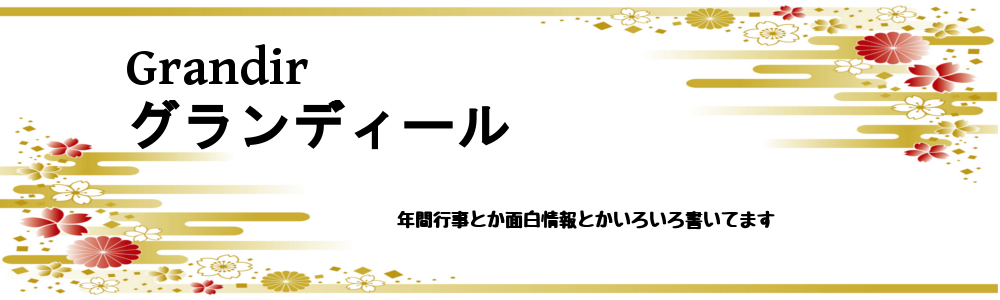
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/160a9cab.0065eefc.160a9cac.2f393adc/?me_id=1296059&item_id=10007592&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsyokusai-shop%2Fcabinet%2Fitem%2Fmainimg2%2F9042_1374023352.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsyokusai-shop%2Fcabinet%2Fitem%2Fmainimg2%2F9042_1374023352.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)










